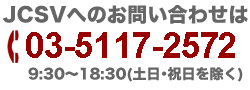円卓会議レポート (「月刊 セキュリティ研究」 218号 掲載)
トランプ新大統領が問う「日本の国体」
一般財団法人 日本価値協創機構(JCSV) 理事長 鈴木 壮治
Concealed Carry License(銃を隠し持てる許可書)を有し、それを「特権ではなく、憲法で保障された自衛の権利」だとするトランプ氏は、選挙期間中、”Peace through Strength”(力による平和構築)と叫び、 また「日本が攻撃されれば、米国は助けに行かなければならない。だが、米国が攻撃を受けても、日本は加勢する義務がなく、日米安保は不公平である」、「日本の核装備は容認する」そして「日本からの米軍撤退」などと声を荒げた。
「個別的自衛権」は、国家の利己的な自衛権ではなく、国民の国家に対する銃を持っての抵抗権であるとの認識を持つトランプ氏の発言は、まさしく、日本の国体「憲法第9条と日米安保の組み合わせによる安全保障」への問題提起である。
北朝鮮による潜水艦発射弾道ミサイルの実戦配備が近づき、昨年の12月14日に、南沙諸島の七つの人口島に、航空機やミサイルを撃ち落とす近接防御システム(CIWS)を配備した中国の“軍事的威圧”と、日本を取り巻く軍事的・地政学的なリスクが高まっている。
そして、トランプ新大統領の「力による平和構築」が米国の安全保障理念となる。よって、日本は、安全保障能力を強化し、国民経済を担う地方経済を再興し、自らの総合的国力を高め、それを十分に発揮できるような体制にしなくてはいけない。
<憲法・日米安保・国連の敵国条項>
憲法の概念ではなく、国際法の概念である自衛権を巡って、個別的自衛権は合憲で、集団的自衛権は違憲とする「論争」をアジア諸国の人々が聞けば、「何だ、日本は自分のことだけ考えていて、友好国の人々が生存の危機に晒されても、憲法を盾にして助けにいかない国か」と思うであろう。
個別的自衛権と集団的自衛権は統合的に活用されてこそ、国の自衛力は高まり、国民を守ることができる。それが「中途半端」であれば問題を生じる。 例えば、今の武器使用基準(PKO参加5原則の第5項)だと、南スーダンへのPKO派遣の隊員(日本国民)は、襲撃されても、定められた手順を踏まないと、相手を撃てず、自らを守ることはできない。 つまり、「最低限の自衛」も許されていないことになる。
憲法の前文中の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」の「平和を愛する諸国民」は、国連憲章で国連加盟国を意味する。
つまり、国連主導の統一的集団安全保障体制に組み込まれる日本は、憲法第9条により、交戦権(国家主権)を放棄しても、安全は保障されるという「理想」を押し付けられたわけである。
国連憲章は「武力行使禁止の一般原則」として、「第7条の集団安全保障」が機能しない場合、その代替として、「第51条の個別的・集団的自衛権」が示されている。その仕組みを使って、自国の安全と生存を維持するが、主権国家である。
よって、1951年、日本が主権回復のために締結したサンフランシスコ講和条約では「 日本国が主権国として、国際連合憲章第51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極(第52条の「地域的取極め」より)を自発的に締結できることを承認する」と定められたのである。
サンフランシスコ講和条約と同時に発効となった日米安保は、両国が国連憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを認めた集団安全保障取極(国連による統一的集団安全保障)ではなく、グループによる地域的集団安全保障である。
サンフランシスコ講和条約と日米安保締結と同時に、憲法を改正し、「集団安全保障と個別的・集団的自衛権よりなる仕組みで、自国の安全と生存を維持する」とすべきであった。
その明記が無いが故に、自衛権の概念は現行憲法に無く、集団的自衛権行使を違憲と政府解釈することにより、日米安保は個別的自衛権のみとして、米国による自衛隊の海外派遣の要請を断ってきた。
憲法第9条を改正して、国家主権としての集団安全保障とそれを補完する自衛権(集団的&個別的)を明記の上、日米安保&地位協定を改定し、国連の「敵国条項」への日本への適用を無くすべきである。
日本の安全保障における主体性回復こそが、アジア太平洋の平和と経済秩序のための「基礎インフラ」である日米安保を強化することに繋がる。
<米国による「核の傘」の形骸化>
戦後、米国の核の傘(拡大核抑止)に守られつつ、「平和国家」を標榜するという矛盾を誤魔化しながら、経済力・技術力で何とか国家としての矜持を保ってきたのが日本である。
その背景には、多くの識者が指摘する下記理由より、独自の核抑止能力を持つよりも、米国の拡大抑止能力に頼ったほうが賢明という日本政府の判断があった。
- 〇 政治的コストが高過ぎる(核開発に反対する大多数の国民と政治的勢力の存在)
- 〇 開発予算が巨大
- 〇 周辺諸国からの反発により、地域の平和秩序が逆に壊れ、日本の軍事的安全保障リスクが高まる
- 〇 小規模の核抑止能力では、敵国の核の先制攻撃に対して脆弱
- 〇 日米安全保障を米国が破棄する可能性
しかし、核の傘は不確実(日本が核攻撃された場合、あるいは核攻撃を受ける恐れが生じた場合、米国が核兵器を使用し、日本を守るかどうかは、その時の米国政府・議会の国家意志次第)であり、戦後、歴代の日本政府は、何とかして、その核の傘の有効性を確かなものにすべく、苦心惨憺してきた。
その一つが「核ヘッジング戦略」(軍事安全保障リスクが高まった場合、速やかに核兵器を開発、自前の核抑止力を持つ)である。要は、米国がしっかりと核の傘を担保してくれないと、独自の核武装に走るぞという「駆け引き」を必死に行ってきたわけである。
例えば、独自の核武装の潜在能力を見せつけるため、プルトニウム再処理の継続、高速増殖炉(大量のプルトニウムを消費する)の開発、衛星打ち上げロケットの開発、そして「自衛に必要な最小限度の実力内の核兵器の保有は合憲」という憲法解釈を内閣法制局が容認してきた。
しかし、中国は、米国の核攻撃に対する第二撃能力(例えば、核弾頭を搭載した潜水艦発射弾道ミサイル・ SLBMを南シナ海深くに潜ませる)を強化しつつある。
中国政府・共産党が、米国と核攻撃に関する「相互確証破壊」の状態を達成、通常戦争と核戦争のディカップリング(分離)が実現したと判断。さらに通常兵器による戦争でも日本に勝利できると中国が思い込み、尖閣諸島強奪の挙に出ることを「想定内」と捉え、日本は自力で尖閣諸島を守り切れる防衛能力を確かなものにすべきである。
<北方領土と国家主権回復>
「北方四島」の「歯舞」と「色丹」は日本の領土として確定している。しかし「国後」と「択捉」は、サンフランシスコ講和条約で日本が放棄した「千島列島」に、「南千島」として含まれてしまっている。
よって、「国後」と「択捉」におけるロシアの権利を認めず、闇雲に「北方四島」一括返還を主張すると、交渉が暗礁に乗り上げることは、容易に想像できる。その様な日本とロシアの鬩ぎあいの中で、昨年の12 月15日と 16日の安倍・プーチンの首脳会談が行われた。
日米安保第6条では「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」とされている。
この条項だけでは、米国は、日本の施政下にある地域に於いては、どこでも基地にできるという「全土基地方式」が認められているとは思えない。しかし、米軍の権利を優先し、米軍基地を「治外法権」とする日米地位協定を知悉するロシアからすれば、日本に返還された「北方領土」に米軍基地が置かれるリスクは看過できない。
そして「日本政府は、返還後の北方領土を日米安全保障条約の適用対象外とする案を検討」と一部メディアが報道した。安倍首相は昨年の10月31日、衆院TPP特別委員会で、北方領土をめぐる日ロ平和条約締結交渉に関連した前述の「報道」に関し、「そのような事実は一切ない」と否定した。政府の日米安保への強い配慮が伝わる「否定」である。
「11月に、谷内正太郎・国家安全保障局長は、ロシアのパトルシェフ安全保障会議書記に面談した際、引き渡し後の北方領土に米軍基地を設置する可能性を否定しなかった」と一部メディアが報じた。それに対し、ロシアのメディアは「北方領土が日本に帰属すれば、米軍基地が置かれる可能性がある」(国営テレビ電子版)と反応した。
それに加え、「ロシア国防省は、軍の部隊が駐留している北方領土の択捉島と国後島に、地上から艦船を狙う新型の地対艦ミサイルをそれぞれ配備した」とロシア・メディアが報じた。
その時点で、安倍・プーチン首脳会談で、北方四島の帰属問題を解決した上で、平和条約が締結されるという多くの国民の一縷の望みは絶たれた。
非対称な日米安保、治外法権を許す日米地位協定に縛られる日本は、ロシアから見たら「半主権国家」であり、ロシアと「親密」となり、中国に対する牽制力を強めることに加え、米国からの独立性を得ようという安倍首相の「思惑」も限界があることを、プーチン大統領は見透かしており、今後の領土交渉も難儀が予想される。
しかし、日本は、旧ソ連時代から、政治と経済を分離し、二国間の経済協力を進めてきた。今回の首脳会談で、北方領土問題解決に至らなかったとしても、粘り強く、民間企業主導の経済協力は推進すべきであり、ロシア側も進出企業への支援、また投資環境の整備に努めてもらいたい。
よって、昨年の12月16日の安倍・プーチン共同記者会見で発表された総額3000億円の8項目(サハリン沖の天然ガス・石油開発など)より成るプロジェクトの担う「国家主権回復への橋頭保としての役割」は大きい。
しかし、日本が米国一辺倒の日本の外交を多元的なものにし、主体性を持って交渉しない限り、北方領土を取り戻し、国家主権を回復することはできないと考える。
<国家主権を侵害するTPP>
大平首相の「環太平洋連携構想」を継いで、中曽根首相が1989年に発足させたAPECは日本主導のアジア太平洋秩序構想である。日本の平和への思いが、APECを広くアジア太平洋諸国に開かれたものにし、APECには、米国、中国も入っており、「秩序安定機能」が期待されてきた。
しかし、APECは協議体であり、法的拘束力が無く、アジア太平洋諸国を束ねるには限界がある。 例えば、APECはFTAをAPEC諸国全体に広げようとしたが、うまくいかず、現在は、そのFTAAP構想をTPPが引き継ぐ形で、その実現を目指してきた。
米国は、中国の台頭に対抗するために、Asia Pivotの一環としてのTPP参加条件を「国家資本主義との決別」として、国家資本主義国家である中国と袂を分かち、APECは分断された。
そして、中国に対抗し、経済成長するアジア諸国を取り込み、日本経済を成長させようと、その流れに乗ったのが安倍政権である。
グローバル企業にとって有利なのが、TPPの「貿易自由化」(知的所有権、政府調達、投資、サービス分野等も含む)であり、それは理想的な市場経済を約束するものではなく、資本主義そのものを体現するものである。
その資本主義の世界では、市場における弱肉強食の闘いの勝者により市場が独占され、その結果、市場原理が効かなくなるという二重律反性を有する。
対日直接投資推進会議が2015年3月に発表した「外国企業の日本への誘致に向けた5つの約束」の一つが、巨額の日本へ投資する外資系企業に相談窓口として、各省庁の副大臣や政務官をつける「企業担当制」である。対象となる企業として、ファイザー、デュポン、IBMなどが選定されており、政府の巨大多国籍企業寄りの姿勢が鮮明である。
また、地域経済活性化といいながら「投資地元からの雇用や物品、サービスの調達を求める現地調達の要求を禁止」の条項を含むTPPは、地域経済の振興策や自治体主導の地域づくりの障害となる。
TPPでは、露骨に巨大多国籍企業の「私益」が優先(ISDS条項など)され、国民経済(雇用など)そして消費者の健康が蔑ろにされることから、米国民にも反発が高まり、TPPに反対するトランプ大統領を生み出した。
また、 TPPの大西洋版とも言えるTTIP(米国とEU28ヶ国)の交渉は、2013年から始まったが、国家主権を侵すISDS条項と食の安全性が脅かされることなどを危惧するEU諸国の国民・市民の声が大きくなり、今年の1月までの合意は、既に断念された。
TPPが頓挫し、中国主導のRCEPの存在感が高まっている。中国がメガ FTAを仕切り、通商ルール策定の主導権を握ることは、日本にとって悪夢である。よって、日本は、新TPP構想(ISDS条項の見直し、食品の安全性重視など)を構築し、その実現を主導していくべきである。
国連の敵国条項(第53条&第107条)を適用されたまま、米国に軍事的依存し、外交・安全保障において米国に追随する日本では、アジア諸国を主導することは難しい。
日本は国際的地位の回復を急がなくてはいけない。
<地方の「周辺化」と官僚主導中央主権体制>
昨年の12月初旬、熊本の震災地を訪れる機会があった。
関係者の話によると「幹線道路の27号線の再開には、あと4年はかかる。回り道は二つあるが、山道であり、冬には凍結し、車の運転はかなり危険となる」とのことだった。
また、「用水路にあるトンネルが泥で埋まり、消火などの用水が確保できず。人手でトンネルの泥を掻き出しているが、トンネル開通の見込みが立っていません」との危機感溢れる説明があった。
熊本地震による被災者住宅の公費解体等への自衛隊の活用に関する民進党の藤末健三参議院議員の質問に対して、安倍首相の答弁書概要は次の通りであった。
「防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施工の委託を受け、及びこれを実施することができる。被災住宅の公費解体等についても、自衛隊を活用することについても、国、地方公共団体等からの事業の施行の委託及びその実施の申出があった場合には、自衛隊法第百条第一項の規定に基づき、防衛大臣が実施の可否を判断することになる」。
自衛隊は、道路などのインフラ復旧工事などで国際的に高い評価を得ており、熊本震災復旧でも、遺憾無くその力を発揮してもらいたい。
日本はどこでも地震が起こりうることに加え、少子高齢化は全国的な問題である。よって、熊本震災は局地的な問題ではなく、日本そのものの問題として把握すべきである。
憲法第13条は「国民は生命、自由及び幸福追求に対する権利を有する。公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」となっている。
熊本地震の「災害被害者担当制」をつくり、副大臣、政務官が、被災者に直接会って、相談に乗ることは、憲法第13条を担う政治家の責務である。その実現が望まれる。
政策・財源・人事で、国は地方を支配している。中央省庁の業務を地方自治体が行う機関委任事務は、都道府県の全業務の70−80%そして市町村の全業務の30−40%に達している。
それなのに、国税60%に対し、地方税30%台に留まっている。それを補うのが、国による「地方支配」を資する「地方交付税」と「補助金」である。 また、憲法でも、国は地方自治体(憲法では「地方公共団体」)を法律で縛っている。
それは、 第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は法律で定める」と 第94条「条例は法律の範囲内」から、明らかである。
地方自治体は「地方公共団体」の境遇に置かれ、予算も施策も政府・省庁に握られている中央集権体制下では、政府がグローバル企業を優遇すると、農業、サービス産業そして中小企業により支えられている地方経済の「周辺化」は進む。
中央集権型官僚統治システムから脱却し、本格的な「地方創生」を実現するためにも、地方分権を体現する「道州制」の導入が必要である。
また、官僚主導の中央集権体制下において、地方を代表する政治は受け身となり、省庁に対する「陳情機関」となり下がったことが、現在の地方の疲弊を生んだと考える。
官僚から、政治が国家運営の主導権を取り戻すためにも、「国会議員の予算提出権」の実現は必要と考える。よって、憲法86条「内閣は毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」を改定し、国会議員も予算提出権を持てるにように明示されるべきである。
地方経済の再興は、官僚主導のコンパクトシティ構想などのようなものではなく、地域の住民、企業、金融機関、中間団体、専門家そして行政が、官僚主導の中央集権体制からの脱皮を理念とした主体的な経済的協働が担うものである。
そのためにも、地方自治という明確な理念が無く、地方自治体を単なる地方公共団体、すなわち「地方における行政サービスを行うことを国から認可された団体」とする憲法第8条を改正しなくてはいけない。
<倫理国家共同体として蘇れ、日本!>
1999年以降、平均所得は20%近くも下落し、相対貧困率はOECD諸国において4番目に悪く、一人親世帯の相対的貧困率は最も高いという惨めな状況に国民生活はある。
政治が、充分機能してこなかったことは明らかである。
日本がデフレに長らく苦しんできたのは、少子高齢化に加え、グローバリゼーションによる影響(例えば、企業の競争力強化のための賃金カット、安い輸入製品の流入など)そしてデフレ時代に、米国の圧力により、構造改革(本来はインフレ対策の政策)導入という致命的な失敗を政府が行ったことによる。
新自由主義の教義により、社会的規制から自由になった市場原理資本主義がバブルを引き起こし、そしてバブル破裂という「自己破壊作用」を繰り返している。その結果、膨大な社会的費用(国民負担)と損失を生じさせる一方、巨額な儲けを得たところに富は偏在し、各国の国民経済を虐げている。
経済成長一本やりの政策(貨幣価値の量的増加としてのGNP成長路線)は、過剰消費を生み出し、商品、設備などの能力が過剰となっている。
その状況を鑑みて、米国の政治学者、ベンジャミン・バーバーは「生活必需品が十分あるのに、奢侈品や嗜好品に対する人々の消費意欲を掻き立て、人々を幼稚化させ、政治を蔑ろにするように仕向けている」と述べた。
私欲に囚われると、共有の倫理思想が育たず、人々は内向きとなり、社会の仕組みを変えようという政治的意志と意欲を失ってしまう。
その結果、政治が国民と遊離し、新自由主義、金融資本主義による経済グローバル化の奔流に対峙し、国民経済を守ることができず、個人の所得・資産格差そして地域格差が拡大し、憲法第13条の「生命、自由及び幸せを追求する国民の権利」そして第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む国民の権利」が侵食され始めている。
互いに助け合うという倫理を日本人は持っている。それは、東日本大地震そして熊本震災における極限的な状況下で、人々は整然と行動し、助け合い、地域社会の秩序を守った姿からも明らかである。そして、その助け合うという社会的倫理により成り立つのが国家共同体である。
安保法制の六つの事態における「存立危機事態 」として「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福権が根底から覆される明確な危険がある事態」とされている。
第13条は、第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と相携えて、震災などによる被災者に適用されるものであり、「存立危機事態」に付き合わせられる類のものではない。
そのようなことを避けるためにも、憲法に集団安全保障とそれを補う自衛権(個別的&集団的)を明確に記載すべきである。
そして、日本は国民の安全と生活を守るため、国家としての主体性を取り戻し、政治、経済そして文化伝統・歴史を包摂する倫理的国家共同体として蘇るべきである。
それこそ、日本の本来の国体である。
雑誌「月刊 セキュリティ研究」(218号掲載)
一橋総研 オピニオン一覧
- 2017年7月7日憲法第9条改正と日本の安全保障
- 2017年5月15日朝鮮半島危機と日本の正念場
- 2017年3月7日リスク化する世界と包括的な安全保障
- 2017年1月13日トランプ新大統領が問う「日本の国体」
- 2016年7月22日遺伝子組み換え食品・農薬―人間・生態系・環境への脅威
- 2016年7月 5日グローバリズムが生むナショナリズム
- 2016年6月29日憲法の変遷理論と九条の無効確認決議について
- 2016年6月27日日本、米国、インドのトライアングルで太平洋の平和と安定の構築を!(雑誌「財界」 平成28年6月7日号掲載)